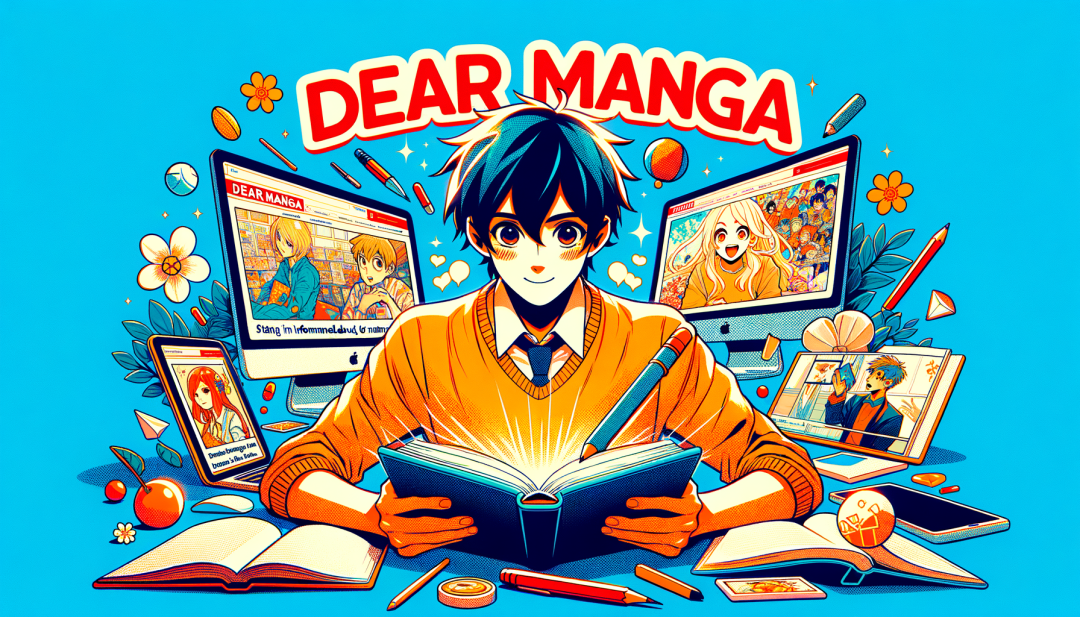「甘み豊かな京野菜!京都府産『万願寺とうがらし』1kgをクール便でお届け -肉厚で甘く、栄養豊富な伝統野菜を食卓に-」
京野菜 万願寺とうがらし まんがんじとうがらし 約1kg (25〜35本前後) 京都産 |京のブランド産品 京やさい 京の伝統野菜 甘とう 唐辛子 トウガラシ 甘長 ショップ:京の老舗の果物屋 鳥羽伊三
価格:2,894 円
|
目次
日本の魅力、「万願寺とうがらし」の秘密に迫る
日本の食文化と言えば、和食の繊細な味わいや、旬の食材を最大限に活かす料理法が挙げられます。
その中でも特に興味深い京都府産の「京野菜」は、多くの食通を魅了する存在です。
その一角を担うのが「万願寺とうがらし」です。
この稀有な野菜が持つ魅力や歴史、そしてその実際の味わいに迫ってみたいと思います。
「万願寺とうがらし」のルーツとその風味
「万願寺とうがらし」は、戦前から京都府舞鶴市の万願寺地区で栽培されてきた伝統ある唐辛子です。
もともとは門外不出の種とされ、その名前に由来します。
一見、「とうがらし」と言う名前からは辛さを思わせますが、実際には「万願寺あまとう」という別名の通り、果肉が厚く、甘みが強いのが特徴です。
この唐辛子の形状は、通常の唐辛子に似ていますが、長さは約13cmと巨大で、非常に存在感があります。
特に、ヘタの下部の独特なくびれが見た目に印象を与えます。
一口食べれば、その瑞々しさと甘みの深さに驚くことでしょう。
果肉は柔らかく、特有の風味を持っており、生で食べることも勿論、様々な料理に活用できる豊富な可能性を秘めています。
食卓に彩りを添える万能選手としての役割
「万願寺とうがらし」は、その優れた甘みと栄養価から、様々な料理に取り入れられています。
焼物としてシンプルに食べることで、その素材の良さを存分に味わうことができ、まさに「和」の心を感じることができます。
また、天ぷらとして揚げても、その甘みが一層引き立ち、食欲をそそります。
そして、「ピーマン」のように肉詰め料理にも適しています。
ビタミンCの含有量が非常に豊富で、食物繊維もたっぷり含まれているため、栄養価も申し分ありません。
健康志向の方には最適な食材です。
こうした特性から、食卓に一品加えるだけで、健康と味の両方を心から楽しむことができます。
料理界と行政の奮闘、「京の伝統野菜」の再評価
昭和40年代になると、宅地化が進み、京都の農家も減少してしまいました。
それに伴い、京野菜は危機に瀕しました。
しかし、京料理界を中心に、その保存と復活のための運動が起こり、行政とも連携して「京の伝統野菜」の定義が定められました。
この活動により、京野菜が再評価され、保存と生産振興が進められてきました。
例えば、「京の伝統野菜」には明治以前から作られていた41品種の野菜が認定されていますが、その一部は残念ながら絶滅してしまいました。
こうした状況を踏まえて、多くの関係者がその価値を大切に守り続けています。
「京ブランド産品」としての価値
京野菜が消費者に信頼されるためには、品質の保証が欠かせません。
そこで、厳格な審査をクリアした「京ブランド産品」として認証された野菜たちは、一流の品質と信頼を得ています。
京都の頭文字「K」をシンボル化したロゴマークがその証です。
「万願寺とうがらし」もその一つとして認められており、他にも「みず菜」「九条ねぎ」「賀茂なす」など、多くの伝統野菜がこのブランドのもとに普及しています。
消費者はこのマークを見ることで、安心してその食材を手に取ることができるのです。
慎重に楽しむ、一部のユニークな個体
万願寺とうがらしを購入する際に一つ注意しなくてはならない特徴があります。
それは、ししとうと同様に、時々存在する「アタリ」と呼ばれる辛い個体があることです。
通常は甘くて柔らかいとうがらしですが、偶に辛みを感じるものに出会うこともあるのです。
こうした偶発的な「アタリ」は野菜ならではの魅力とも言えますが、購入の際にはこの点を理解し、気をつけて食すことが求められるでしょう。
しかし、この多様な顔を持つ万願寺とうがらしだからこそ、料理には一層の楽しみと発見をもたらします。
まとめ:「万願寺とうがらし」を家庭の食卓へ
「万願寺とうがらし」は、その豊かな風味と栄養価から、日本の食卓に欠かせない食材となり得る存在です。
何世紀にもわたる歴史と共に培われた京野菜の魅力をお楽しみいただけます。
野菜の持つ本来の味を感じながら、シンプルな料理法で堪能する贅沢。
それはまさに豊かな食文化を築く一歩です。
日本の伝統と滋味深さを味わう機会を逃さず、ぜひ一度「万願寺とうがらし」を試してみてください。
その美味しさにきっと驚かれることでしょう。
ショップ:京の老舗の果物屋 鳥羽伊三
価格:2,894 円
|
2025年7月14日
関連記事
小学生のまんが慣用句辞典 単行本 の詳細 出版社: 学研 レーベル: 作者: 金田一秀穂 カナ: ショウガクセイノマンガカンヨウクジテン / キンダイチヒデホ サイズ: 単行本 ... 2026年2月11日 マンガ |
まんがくらべるワールド!危険生物 単行本 の詳細 カテゴリ: 中古本 ジャンル: 産業・学術・歴史 動物 出版社: 小学館 レーベル: 作者: 春風邪三太 カナ: マンガクラベル... 2026年2月11日 マンガ |
中学入試まんが攻略BON! 算数 つるかめ算 【新装版】 単行本 の詳細 カテゴリ: 中古本 ジャンル: 産業・学術・歴史 数学 出版社: 学研教育出版 レーベル: 作者: 学研... 2026年2月9日 マンガ |
まんがでわかるLIFE SHIFT 2 単行本 の詳細 出版社: 東洋経済新報社 レーベル: 作者: ScottAndrew カナ: マンガデワカルライフシフト / アンドリュースコット サイズ: ... 2026年2月9日 マンガ |
著者:幡地 英明, 星井 博文, 浅田 弘幸, 高橋 典幸出版社:集英社サイズ:単行本ISBN-10:4082391061ISBN-13:9784082391065■こちらの商品もオススメです ●あたしンち(第10巻) / けら え... 2026年2月8日 マンガ |